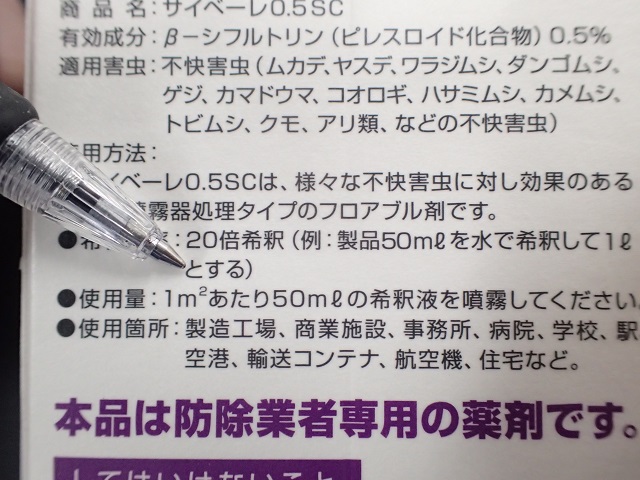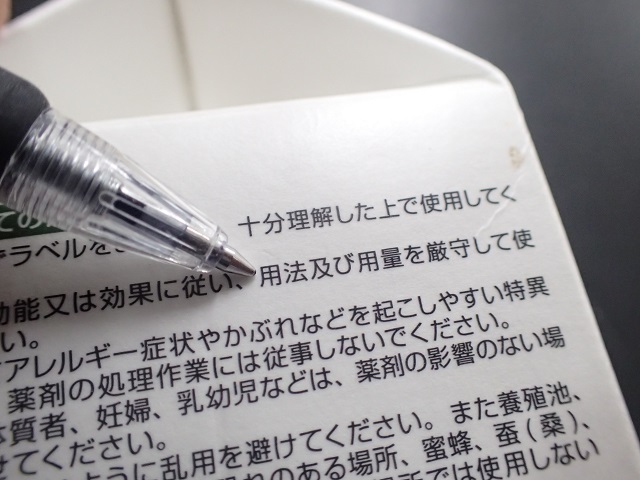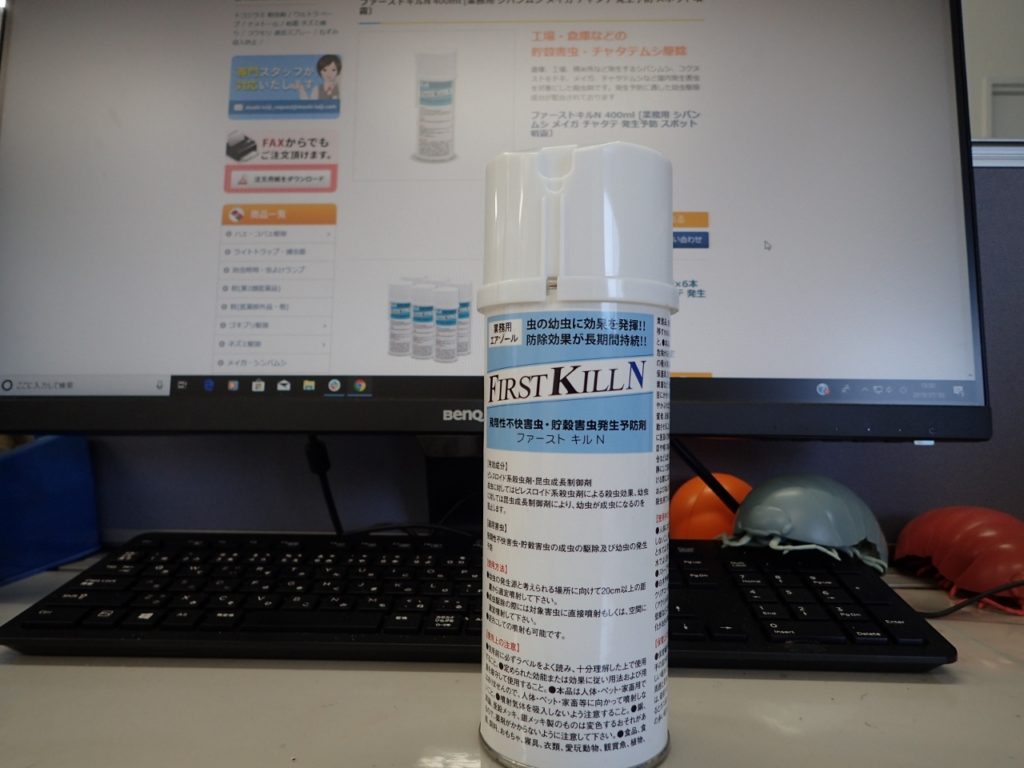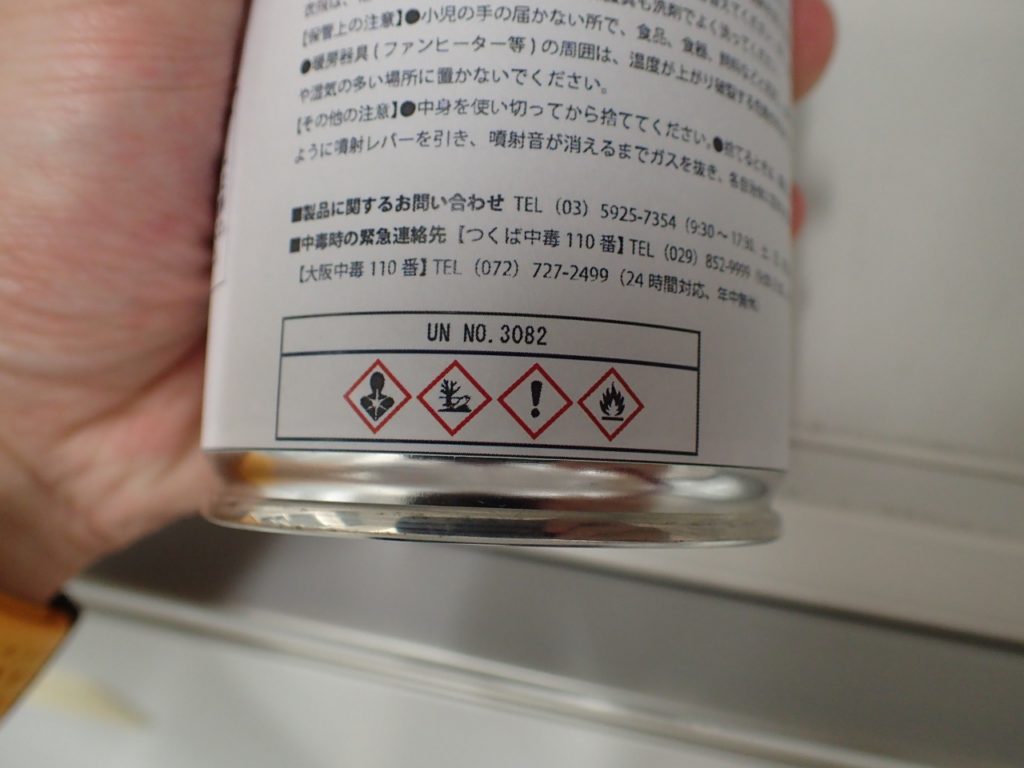このたびの豪雨に被災された皆様へ心からお見舞い申し上げますとともに、救護・復旧作業に従事されている皆様の安全をお祈りいたします。
成虫の次は幼虫(ボウフラ)退治
蚊を退治する上で大事なことは何か?もちろん飛び回る成虫への対処も挙げられようが、それ以上に幼虫、すなわちボウフラが湧いている場所を無くすことが重要である。可哀そうだが根絶やし作戦である。では次に蚊が湧く場所はどこかという疑問が湧く。端的に言えば、落ち葉などが溜まっている水たまりである。具体的には以下に記す通りである。

1.植木鉢の受け皿
まずは外に置かれた植木鉢である。大抵は下に受け皿が敷かれている、あるいは鉢カバーの中に入れられているという具合であるが、これに注目したい。

受け皿や鉢カバーの底に落ち葉と雨水が溜まっていないだろうか。というのはボウフラは水の中に生息し、そしてそこに溜まった落ち葉や泥といった有機物を食べて育つ。つまり、こんなところはボウフラにとって生活しやすい場所なのである。

では、そんな受け皿や鉢カバーをどうするか?簡単である。水洗いしてボウフラもろとも中に溜まった水と落ち葉をきれいに洗い流し、そして乾かすだけである。だがしかし、雨が降ると再び水がたまり、そして時間とともに落ち葉や泥も溜まることには注意が必要である。できれば月に1回を目安に溜まった水と泥を捨てる作業を繰り返したい。

2.地面に長い間放置されている物
では次に下の写真である。筆者が高校生の頃、亀(イシガメ)の飼育に使用していたコンクリートのトロ舟である。今は時々お花の植え替えをする時に土と肥料とを混ぜる以外には使われておらず、長い間伏せられたまま置かれている。

このトロ船をよく見ると裏面に凹凸が多く、泥や水が溜まりやすい構造であることが分かるであろう。そしてそこが小規模ながらも蚊が湧く場所になることは容易に想像がつく。事実、調べてみたところ手前の凹凸部にボウフラが数匹生息していた。

この場合も全体を水できれいに流す、タワシで泥を落とすなどした後、乾かしておく。そして使わない、または年に数回しか使わないのであれば物置に収納しておくのがよいであろう。

3.ビニルシートの水たまり
それと変わった事例の紹介である。これは雨除けカバーをつけた自転車であるが、カバーをつけたまま長い間放置されていた。そして、である。自転車のカゴのところを見ていると、そこに水と落ち葉が溜まっていた。こんなところも蚊が湧くかもしれない場所として要チェックである。

この場合も難しく考える必要は無い。自転車から雨除けカバーを外して水と落ち葉を落とす、そして綺麗に洗って干す。そしてまた自転車にかけ直す。以上で解決である。ただし、カバーを外す時に落ち葉とか色々な物の混じった生ぬるい水が一気に流れ出してくる。自分にもであるが、まず周囲の人に水をひっかけないように注意したい。

4.コンクリートブロックの中
さてさて、しつこく蚊が湧くであろう場所探しを続ける。今度は庭木や雑草が生い茂っている場所である。汚れる、痒くなる、色々と億劫であるが、これらの葉をかき分けて地面に何があるのかを調べたい。思わぬ蚊の隠れ家が見つかることもある。

これは庭木の影に隠れていたコンクリートブロックである。穴のところに雨水と泥が溜まっていた。蚊の格好の住み家である。いささか面倒であるが水を捨てるとともにゴミをほじくり出し、水はけをよくしておく。あるいは水が溜まらないように横へ倒してしまってもよいだろう。

5.大きな金魚鉢や水瓶の中
なかなか無いと思われるが、写真のような水瓶がある庭は注意したい。雨水や周りの庭木から落ちた葉っぱがすぐに溜まってしまい、蚊にとっての優良物件である。特に金魚やメダカを飼っている訳でも無く、水が溜まるにまかせているようであれば赤信号である。

案の定、中を覗いてみると大きく育ったボウフラが十数匹見つかった。これは駆除のし甲斐がある。そう思って眺めるうちに、ふとほくそ笑む自分の顔が水面に浮かんでいることに気づいた。傍から見れば、どちらが正義か悪か分からない構図である。

さて、話を元に戻す。これはどう料理すべきか?排水ポンプでボウフラごと水を捨ててしまい、後で底にたまった落ち葉や泥をさらう方法が挙げられる。しかし、それは面倒である。おまけに時間とともに雨水と落ち葉が再び溜まってしまい元の木阿弥である。そこでこんな時は水底に沈んで殺虫成分を出し続けるスミラブ粒剤を利用したい。詳細は商品ページに譲るが、ここはこれで解決である。

6.庭の雨水桝
最後に、庭にあることすら忘れ去られた雨水枡に触れたい。ここも蚊が湧くかもしれない場所に挙げられる。過去に友人宅にて蚊の被害があり、雨水桝の見落としを指摘したところ博識な彼をも唸らせ、また喜んでもらえたのはプロとして何とか冥利に尽きるというものであった。

さて、その中はどうなっているか。開けてみると水や泥が溜まっており、蚊が発生できる状態とも言えなくもない。何かしら対策は講じておきたい。この場合も先ほどと同様にスミラブ粒剤を散布しておくとよいだろう。

なお、日曜大工が得意な方のご自宅でよく見るのがこちら。雨水枡の穴にきちんと メッシュを張り、蚊の侵入を防止できるようにしているものである。これは大変効果的である。お見事と賞賛の声を送りたい。

ただ、それでも気を付けたいのは蓋の隙間である。砂利が挟まって蓋がきちんと閉まらないようであれば、そうして生じた隙間から蚊が雨水桝の中へと侵入して産卵し、ボウフラが湧くケースもある。きちんと蓋が閉まるよう清掃を心がけたい。

以上、蚊に限らずであるが、清掃や片付けの行き届いていない場所があると何かしらの害虫が発生する。害虫駆除とは殺虫剤の散布だけにあらず、整理整頓も大事であると心得たい。ところで、庭には先ほど使用した殺虫剤や、その散布に使う道具が散らかったままである。そろそろ親に見つかる頃だと思ったところで本日は筆を置かせていただきたい。