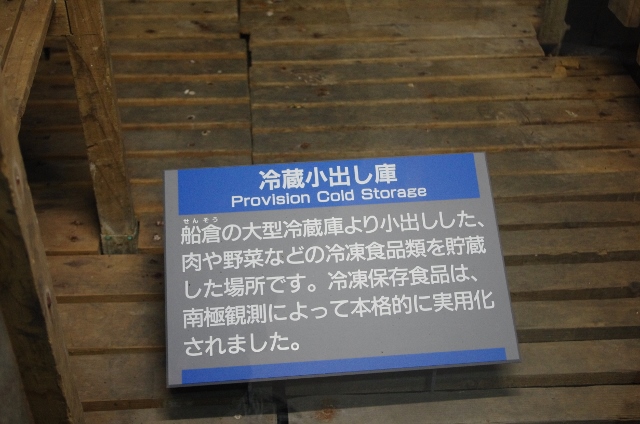「トラックの数、これでもまだ少ないかな」 運転席で一人尋ねた帰り道

運転が楽しいと思い始めたら、ある日視界がおかしくなりました。 お医者さんが大丈夫と言ってくれた通り、また見えるように戻って くれたけれど、運転も下手に戻ってしまったな・・・まあ、いいさ。 それでも、また運転席にいられることが素直に嬉しいなと思います。

さて、現場帰りの大きな国道。対向車線のトラックを見て思い出す 父の言葉。「これでも昔に比べてまだまだ少ない」というかな? 夕日に染まる道路、サイドミラーの端へ流れていくトラックたち、 ふと想像するその積み荷。 会社で商品出荷の様子を見てるから、ついつい樹脂製のパレットと その上に積まれたたくさんの段ボールを思い浮かべてしまう。 それと同時に考える余計な事。パレットに何か変なものが付着して ヨソへ持ち込まれたりしていないかな。

でも実際、疑いの目をもって見ればパレットにクモの巣が張って いたなんてことはあるし、そこに生きたクモがいたらパレットや トラックなどを介して他の場所へと運ばれてしまう。 その他にも例えば、パレットにカビが生えていたり、小麦粉とか 食品原料が堆積していたら、それらを餌にする虫たちが発生して しまう。 そして最悪の場合はどうなるか、それは・・・予期せぬ場所での 異物混入の事故。

それを避けるには、日頃から定期的にパレットを目視点検する、 掃除する、時間が無いのだとしてもコンプレッサーのエアーで 汚れを吹き飛ばすなどし、予防に努める必要があります。

それと掃除の仕上げとか、突然出てきた虫へ対処しないといけない 時のために速乾性で安全性も高いスプレー剤を常備しておいても いいかなと思います。「有機JAS資材評価協議会 資材リスト」に 登録されているから、オーガニック加工工場での使用もOKです。 こんな物もあるんだってこと、もし興味を持っていただけたり、 お手に取っていただけたら幸いです。
担当者の独り言
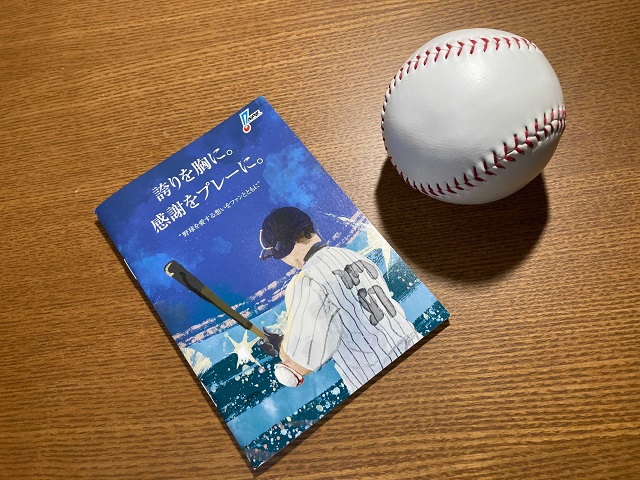
プロ野球のペナントレースも、とうとう終わり。それに合わせて いぶし銀のベテラン選手も、長く球場の運営を支え続けた方も、 次々と惜しまれながら引退して、球場へ別れを告げる。 僕にもいつかは最後の登板日が来る。それが思ったより早いのか、 それともうんと遅いのかは分からないし、不安は尽きない。 でも、いよいよその引き際に「矢弾尽き果てた」って言えたら いいなと、去り行く背番号を見て思います。同時に選手生命を 縮めないよう、些細なことは適度に笑ってごまかしていけたらと 思います。