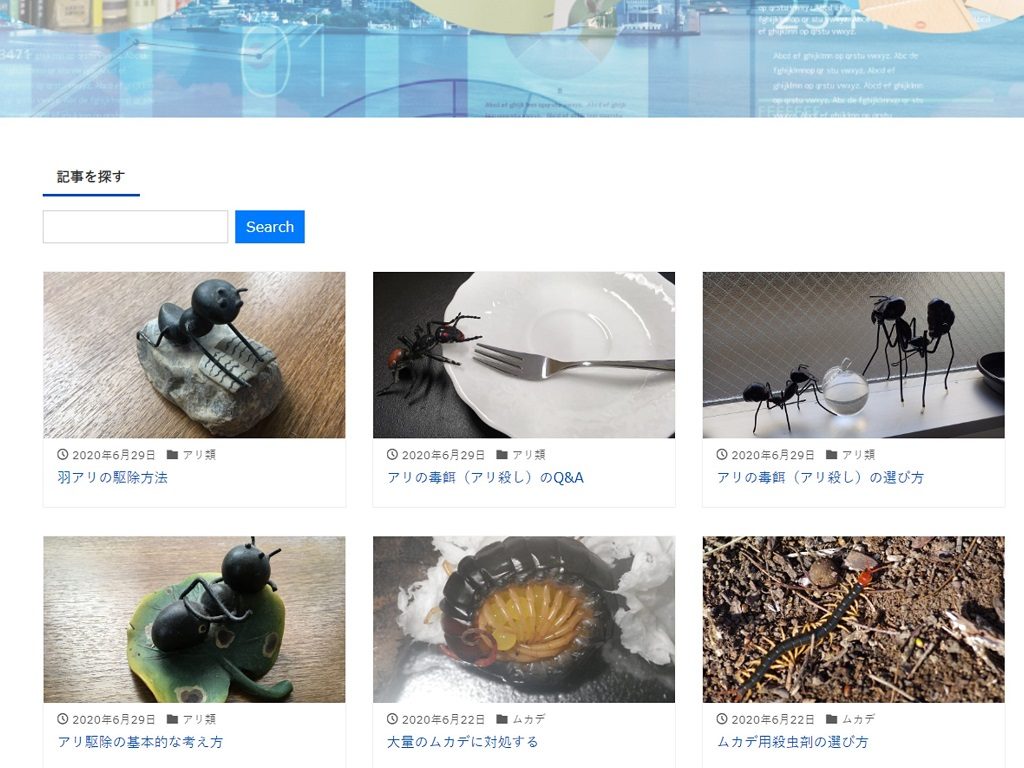そろそろ素麺とか、にうめんが主食になるであろう男が書くブログ
「家の中」で「アリみたいな虫」に「刺される」
■ それは本当にアリだろうか?

最近気になる虫のお問い合わせがありましたので、本日の話題にしようと思います。 上の写真はシバンムシアリガタバチと言い、名前の通り「アリの形をしたハチ」です。 素麺などの乾麺、乾燥シイタケ、切り干し大根といった乾燥野菜、他にもお茶の葉や 菓子類などから発生するシバンムシ類に寄生する昆虫です。 人に寄生することはありませんが、「そこに居ると知らずにうっかり触れる」と 反撃で「プスリッ」と刺されることがあります。 「家の中」で「アリのような虫に刺された」という場合、本種の仕業であることが 多いです。
■ 宿主となるシバンムシ類への対策が重要
このシバンムシアリガタバチを駆除する場合、殺虫剤の散布だけでは解決しません。 それに加えて彼らの宿主であるシバンムシ類もきちんと駆除しなければなりません。 では、その「シバンムシ類を駆除するためのキーポイントは何か?」といえば 発生源となる物を清掃・除去することでしょう。

「発生源の清掃・除去」といっても難しいお話は何もなく、保存食品を保管 している棚とか机の周りを掃除機などを用いて掃除するだけです。 特に上の写真のような台所のキャビネットは真っ先にチェックしましょう。 底のところに細かい食品屑が溜まっていたら、掃除機で全て吸い出します。

また、「食品をジップロックで保管する」や「ビニル袋に入れて輪ゴムで口を 縛る」というのは封ができているようで実は虫の目からは隙間だらけです。 そのような管理をしているとシバンムシ類が食品から湧いてしまう原因にも なりますので、ネジ式の蓋のついた瓶などで保管するのが正解です。

それと上の写真のように「上から引き出すことができるキャビネット」の場合、 機構が少し複雑になっているため、基部のところにも食品屑が溜まります。 事実、ここではシバンムシ成虫の死骸が4体見つかり、小規模ながら発生源に なっていたことが伺えました。 普段何気なく視界に入る場所ですが、このようなところも掃除機でしっかり 清掃しておきましょう。
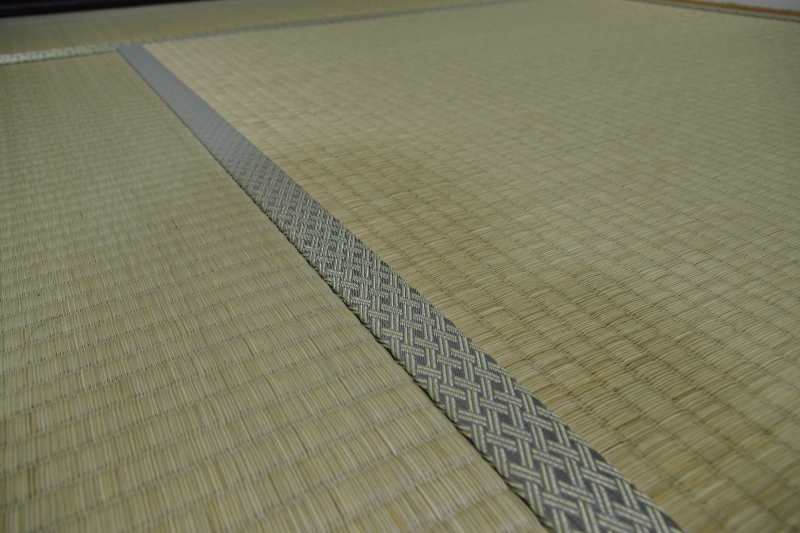
最後に、シバンムシ類は「乾燥した植物質であれば何でも加害する」という性質から 「畳のイ草」をも食害します。 筆者の経験では「なかなか畳からシバンムシ類が発生しない」との印象がありますが 発生源としてマークしておく必要はあるでしょう。 特に畳の表面にボールペンで刺したような丸い小さな穴が複数あれば少し注意です。 シバンムシ類の成虫が畳の中から羽化する際にあけた穴の可能性があるためです。 こんな時は調査の上、畳ごと交換してしまうのがよいでしょう。
■ 殺虫剤はどんなものを使用するのか?

シバンムシ類の駆除を考えた時、厳密には「幼虫の発生を予防するような殺虫剤」を 使用するのがセオリーです。 しかし食品工場と異なり、一般家庭の場合は清掃による発生源対策がきまりやすく、 そこまで本気の殺虫剤処理が必要なのか少し疑問です。 まずは清掃後に仕上げとしてバルサンなどの燻煙剤を利用する、あるいは撃ち漏らした 成虫がひょこひょこと出てきた時に「安全性が高く、べたつきも残らない殺虫剤」で 個別に駆除する方法でもよいと思われます。 以上、タイトルとは違ってシバンムシ類への対策が中心の記事になってしまいましたが、 こうすることでシバンムシ類ごとシバンムシアリガタバチを駆除することができます。 ただ「それでもちょっと不安だなぁ」という場合はお気軽にお問い合わせください。 色々とお聞きするので少しお電話が長くなるかもしれませんが、最適な対策をご提案 させていただきます。
■ 担当者の独り言

旅のプランはよりどりみどり、誘惑が非常に強かった4連休でしたが外出したい気持ちを ぐっと堪えてステイホームを遵守しました。 投じられた真ん中高めのストレート、息を呑んで釣り球を見送り、次の一球へと繋げる。 本格的な野球の経験者ではありませんが、そんな思いでした。

しかし、それだとストレスが溜まる一方なので、会社でいただいた旅行の冊子や 過去の旅行写真を眺めて気分を紛らわせていました。 今回は旅先で食べたあれこれについて整理・・・僕も少しお腹がすいたなぁ。

休日も資料作成に励むのはよいことですが、何かしらのアクセントも時には必要。 僕も料理、やってみようかな・・・。