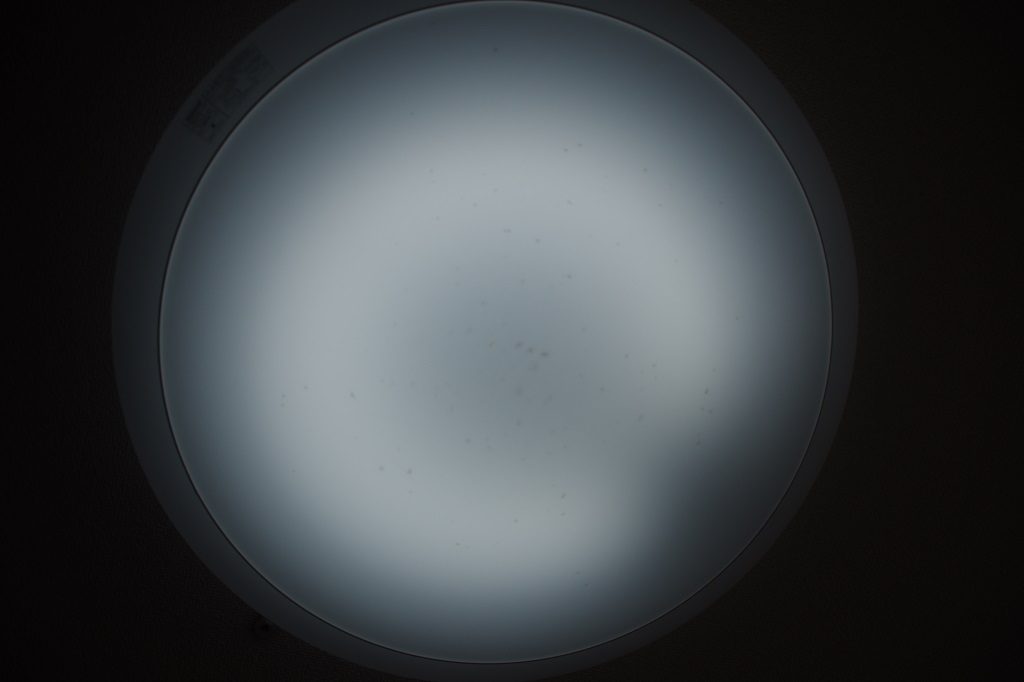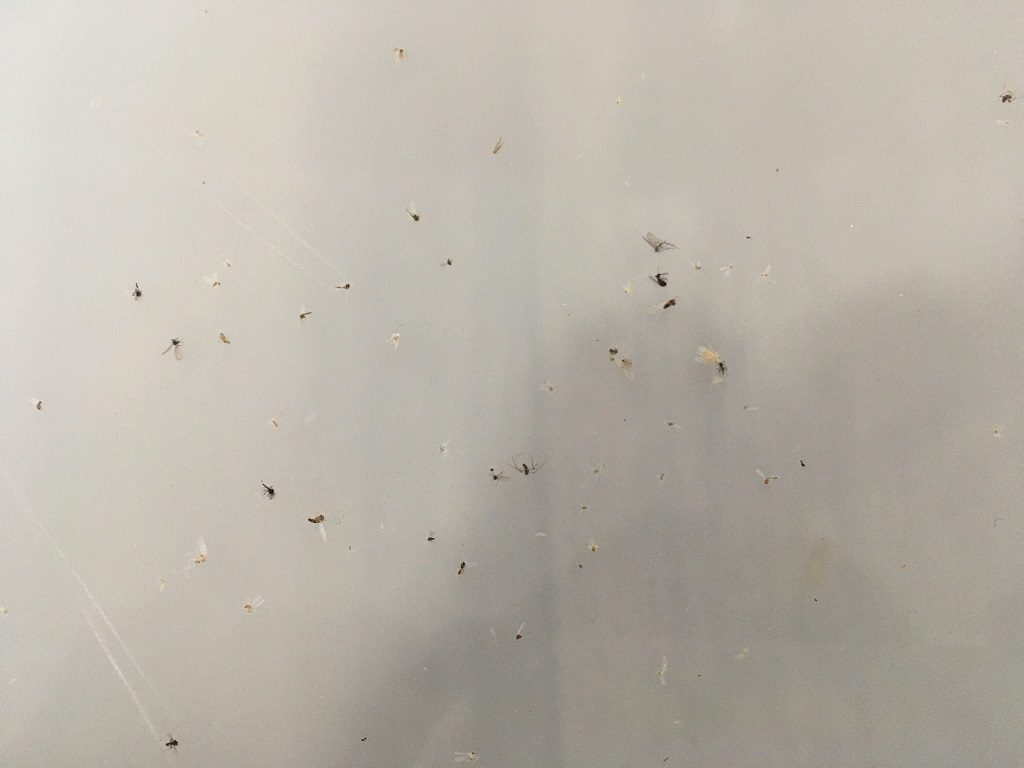久しぶりに道端でこけた男の物語

コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出できないためかどうか定かではありませんが、 外でランニングしている人をよく見かけます。 私も人が少ない時間帯に時々走っていますが、某日うっかり道端で転んでしまいました。 どうやらアスファルト面とコンクリート面との間に段差があったらしく、そこに足を 引っ掛けて転倒したようです。

小学校の頃は「手をポケットに入れて走るな」と「こけた時に手をついて頭を守れ」と 叱責され指導を受けますが、そのような経験はこんな時に活きてきます。 右足に衝撃とともに鋭い痛み、転倒を悟ると同時に眼前へ迫る白いコンクリートの地面、 膝をガリガリと地面が削り取っていく感覚、その中で反射的に出した手。 加賀マラソン参加記念の手袋は、私の身代わりとなってズタズタになってしまいましたが 頭はかすり傷一つなく済みました。

膝から血液やら黄色い汁やらが垂れたまま帰宅、ここまで大きな傷を負ったのは 幼稚園以来ではないかと思います。 しかし走る機会が増えれば、その分転倒などの事故を起こす可能性も上がるため 今後も気を付けなければなりません。 そしてそれはネズミの場合も同様で、天井裏などに粘着板を敷きつめたままにすると その分だけネズミが引っ掛かる確率は上がります。 グルットプロシリーズの粘着板であれば、どれも半年くらい天井裏に放置しておいても 捕獲力が失われないため、そのような敷き詰めっぱなしの作業には適しております。